チョンオ(青魚、ニシン、鰊)は長い間、世界の人々の主要な食糧となってきた魚だ。最近韓国では海風に日干ししたチョンオを海苔やワカメ、ニンニクなどを添えて、野菜に包んで食べる「クァメギ」の人気が高い。その他にも古くから様々なニシンの料理法が伝えられてきたが、独特な歯ごたえと脂ののった香ばしさで、冬の珍味として挙げられてきた。
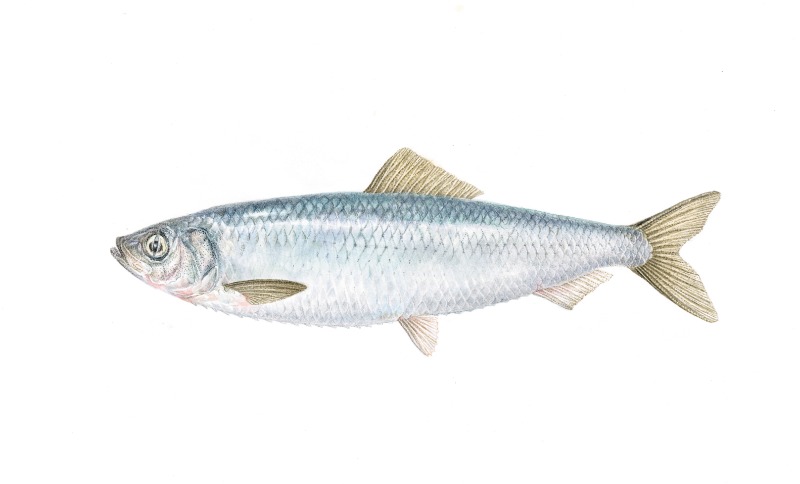
チョンオ(青魚、ニシン)は、世界の多くの人々になじみの深い魚だ。身が細く厚みはあるが、背面は暗青色、中央から腹部にかけては銀白色の青魚の一種だ。水温2~10度、水深0~150mの寒流が流れる沿岸に群れを作って生息している。朝鮮半島沿岸のニシンの収穫量は非常に不規則だが、今年の冬は豊漁を記録している。
「美味しさではチョンオ、たくさん食するのはミョンテ」という言葉が伝わっている。韓国人の食卓にのぼる代表的な三種類の魚―テグ(鱈・タラ)、ミョンテ(明太・スケトウダラ)、チョンオ(鰊・ニシン)―の中で、味はチョンオが一番だという意味だ。
読んで字の如し「体の青い魚」という意味のチョンオは、いろいろな種類が巨大な群れを成して海中をあちこち回遊している。北欧でよく食べられているニシンは北大西洋ニシン、北東アジアと北米のものは太平洋ニシンと呼ばれる。
白身の魚であるタラやスケトウダラは脂肪が少ないが、ニシンは脂肪が豊富で、多いものでは20%にも達するという。寒海性魚類のニシンは冬から春が産卵期で、晩秋から脂がのってくる。その他の特徴としてグリシン、アラニンのように甘味を出す遊離アミノ酸が豊富に含まれている。
1803年にキム・リョ(金鑢、1766-1821)による韓国最初の魚譜『牛海異魚譜』には、ニシンの味について「甘く柔らかく、焼いて食べると非常に美味しい」と書かれている。調理士であり作家のパク・チャニル(朴賛日、1965-)もニシンの味について同様の表現をしている。彼はその著書『追憶の半分は味だ』で、束草の海辺の刺身屋で友人と食べた焼きニシンについて「風の冷たい冬の日に、荒塩を振って炭火の上で焼いたニシンの身は柔らかく甘かった」と回想している。
料理方法
ニシンは食べ方も様々だ。主な産地の東海岸では刺身や刺身の和え物にして食べるが、時には湯がいたニシンの身を裏ごし、うるち米を入れて粥にして食べたり、小麦粉と卵をつけて焼いた後、すまし汁を作り煮込んで食べたりもする。東南の海岸に面した慶尚道地方ではチゲにして食べたりもする。西南の全羅道地方では大量のニシンを料理するときに釜で湯を沸かして、その水蒸気で蒸してコッチュジャンを付けて食べたという記録もある。しかし、ニシンは塩焼きにするのが一番おいしいと言える。 荒塩を振って、焦げ目がつくまで焼くと身が柔らかくなり、甘く香ばしい。調理士パク・チャニルは『脂ののった魚なので焼くとじゅうじゅうと脂がにじみ出て最高の味が楽しめる』と書いている。
海水魚には、海水と体内の塩度のバランスを保つ非タンパク質窒素化合物のトリメチルアミンオキサイド(TAMO)が含まれている。この化合物が微生物によってトリメチルアミン(TMA)に分解されると生臭くなる。冬の脂がたっぷりのったニシンには多価不飽和脂肪酸がたくさん含まれており、簡単に酸敗してしまう。そのため生臭さがより一層強くなるが、チゲを作るときに味噌を入れたり、焼くときに味噌を塗ることで生臭さを消すことができる。味噌の中の香り成分が生臭さをあまり感じさせないようにし、味噌の主成分であるタンパク質が生臭さの成分と結合して揮発を防ぐからだ。
しかし1990年代以降、ニシンの様々な調理法を見ることが難しくなった。実際に1996年1月27日の東亜日報には「ニシンのチジミ、ニシンの煮つけ、ニシンの塩辛、ニシンの白茹でのような京畿道式の料理を最近ではほとんど目にすることがない」という記事が掲載されている。
様々なニシン料理を味わうのが難しくなった最も大きな理由は、ニシンを獲るのが難しくなったからだ。ニシンの漁獲量は昔から年によって大きな差があった。冷水にのり群れを成して移動するニシンは、時には年間最大漁獲量を記録するほどだった。一方で不漁の続いた10年間は、全く姿を見かけないこともあった。壬申倭乱(文禄慶長の役)を回顧したユ・ソンリュン(柳成龍、1542-1607)の『懲毖錄』には、戦乱が起きる直前に起きた奇怪な現象だとして次のような記録がある。
「東海の魚が西海で獲れ、だんだんと漢江にまで達し、もともと海州で獲れていたニシンが最近10年以上もまったく獲れず、遼海に移動して獲れるので、遼東の人たちはこれを新魚と呼んだ」。
同時期の1614年にイ・スグァン(李睟光、1563-1629)が書いた百科事典的な著書『芝峰類説』にも似たような説明が出てくる。春の頃、西南の海でいつも多く獲れていたニシンがなんと40年間全く獲れなかった、というのだ。しかし、イ・スンシン(李舜臣、1545-1593)将軍の『乱中日記』には、ニシンを獲って兵糧と交換したという記録がある。
実学者イ・イク(李瀷、1681-1764)は著書『星湖僿説』で、柳成龍の『懲毖錄』を引用しながら、こんな状況を説明している。 柳成龍の『懲毖錄』が書かれた当時には黄海道の海州にだけいたニシンが、今では朝鮮の海の全域で獲ることができる、というのだ。彼はニシンが「毎年秋頃になると咸鏡道で獲れ」さらに「春になるとだんだんと全羅道と忠清道に移っていく。春と夏の間には黄海道で獲れたが、だんだんと西に移りながらどんどん増えていき、そのため希少ではなくなり、食べたことのない人間がいないほどだ」と記録している。

ニシンを冬の海風にさらしながら乾燥させた「クァメギ」は、もちっとした歯ごたえと口いっぱいに広がる魚油の香ばしさは絶品で、冬にしか食べられない特別な食べ物だ。よく乾燥させたニシンを薄く切りニンニク、青唐辛子、ニンニクの芽などを細く切り、ワカメやノリで巻いて食べる。
© Getty Images Korea

冬になると慶尚北道盈徳(ヨンドク)をはじめとする東海沿岸の漁村では、ニシンを乾燥させるのに忙しい。頭を切り落とし、冬の海風にあてて日干しするので凍ったり、溶けたりを繰り返しながら生臭さがとれ、香ばしいクァメギが誕生する。
© チョン・ジェホ(田財浩)
クァメギ
イ・イクは時代別の漁獲量が大きく変わり、獲れる地域さえも変動しているのは、ニシンが風土と気候の変化に伴って移動しているからだと推測した。250年前の説だが、彼の推測は正しかった。国立水産科学院が1970年から2019年までの朝鮮半島沿岸のニシンの漁獲量を分析した結果、東海では水温が上がれば上がるほど漁獲量が増加した半面、西海の漁獲量は水温が上がるほど減少した。
この研究によればこの50年間、ニシンの漁獲量は非常に不安定な状況だった。1970年代の初めまでは年間5千トンほどだったのが、中頃になると1千トン未満に落ち込んだ。1980年代末からは再び増加し、1999年に頂点に達し2万トンを記録、再び2002年には2千トン以下に落ち込んだ。2000年代中頃から再び漁獲量が急増し、2008年には4万5千トンに達した。その翌年までニシンの豊漁は続いた。2009年12月20日のKBSニュースは「消えたニシンが戻って来た」というニュースを伝えている。寒流性魚種のニシンが東海だけでなく水の温かい東南海と南海沿岸でも多く獲れるようになり、慶尚北道盈徳ではニシンの「クァメギ」が再び作られるようになったと報道している。
1960年代以降ニシンが獲れなくなり主に慶尚北道の海岸地方では、サンマでクァメギを作るようになったが、もともとクァメギはニシンを干して作っていたものだ。魚類学者のチョン・ムンギ(鄭文基、1898-1995)が1939年5月9日の東亜日報に書いたコラムによれば「ニシンの多産地である慶尚北道では短期間干したニシンの干物をクァメギと呼んでいる。地元の特産物として大切にされている水産物」と説明している。
このように1930年代の慶尚北道の海岸地域はニシンの主産地だった。最近ではクァメギを白菜のような葉物野菜や、ノリ、ワカメ、昆布のような海藻で包んで食べる店が多いが、昔は火で焼いたり、スックック(ヨモギ汁)にして食べたりした。
クァメギという呼び名がどこから来たのかははっきりしない。朝鮮後期の実学者ソ・ユグ(徐有榘、1764-1845)の著書『佃漁志』によると、当時の朝鮮の干しニシンは背中を裂いて開くことはせずに、そのままわら縄を貫通させて結び日向で干して作っと説明している。ソ・ユグは、二つの目が透明で、縄で貫通して結ばれているので「貫目(クァンモク)」と呼ばれていたと主張した。この言葉が変化して今のクァメギとなったという説がある。
ニシンをそのまま干す「トンマリ方式」のクァメギは、少数ではあるが今も受け継がれている。一方大部分のクァメギは、腹を半分に開き内臓や骨を取り除いて海風に短期間干して乾燥させた「ぺチギ方式」だ。トンマリ方式のクァメギの乾燥時間が長くかかるのは、サンマよりも脂がのっており、体長も大きいからだ。サンマ一匹の乾燥期間が15日ほどかかるとすれば、ニシンのトンマリ方式は1カ月以上の期間がかかる。しかし、長い間乾燥させるとそれだけ味に深みが増し、一冬を通してそのまま乾燥させたトンマリ方式のニシンのクァメギには卵も入っており、より一層美味しい。

きれいに洗ったニシンの鱗をとり、両面に隠し包丁を入れて荒塩を振り、 じっくり両面をこんがりと焼くと、甘く香ばしい風味となる。特に脂ののったニシンは、焼くと淡白さが増幅され、身は柔らかくなり口の中で溶けるようだ。ただ小骨が多いので少し面倒ではある。
© Shutterstock
戻って来たニシン
ニシンが戻って来た。今年もニシンがたくさん獲れている。江原道三陟ではニシンの消費を増やすためにオデン、煮物、天ぷらのような様々な加工方法も研究されている。国立水産科学院の研究によれば、2000年代以降にニシン漁獲量が増えているのは、主に東海の水温が温かく変化してニシンの個体数が増えているからだという。
しかし研究者たちは、このような研究結果がすなわちニシンの乱獲を認めるものではないと警告する。北大西洋で乱獲によりニシンの漁獲量が急減してしまった前例から、ニシンの稚魚を獲らないように禁止する管理が必要だった。1970年代ノルウエーでは乱獲によりニシンの漁獲量が0トンにまで急減してしまい、以前の水準にまで回復するのに20年もの歳月が必要だったという。記憶しなければならない先例だ。
ニシンが正確にどのようにして群れを成して移動しているのかについてもまだ分かっていない点が多い。ニシンが東海に戻っては来たものの、近海の中国黄海や日本の北海道では依然として獲れていない。我々は未だに、このような現象が起きる理由についてよく分かっていない。無分別な乱獲よりは謙虚な心でニシンを、そして自然を見守る態度が必要だ。