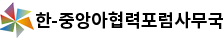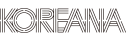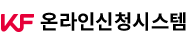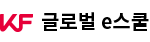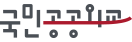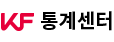Features
-

Features 2024 SUMMER
都心に息吹を与える公園 ソウルの森は、聖水洞(ソンスドン)のまた違った表情が見られる空間だ。韓国で初めて市民が公園づくりに参加して、2005年にオープンした。35万坪の園内は文化芸術公園、体験学習園、生態の森、湿地生態園と特色ある四つのエリアで構成されており、地域の生態や地理的な特性を生かして都心の代表的な憩いの場になっている。 漢江と中浪川の合流点につくられたソウルの森。上空から見ると三角形だと分かる。自然の生態系が保存され文化施設も整っているので、都心の憩いの場として人気だ © ソウル研究院#聖水洞(ソンスドン)
-

Features 2024 SUMMER
偶然ではなかった キム・ジェウォン(金才媛)氏は、ブランド設計やコンサルティングを手がけるアトリエ・エクリチュールの代表を務めている。ソウルの聖水洞(ソンスドン)で複合文化施設チャグマチを2014年にオープンし、その後10年にわたって個性的な空間を企画・運営することで同地の変化をリードしてきたと評価されている。 カフェ・チャグマチ。印刷所の痕跡を生かして内部をリノベーションしたもので、オープン当時としては珍しく講演、展示、ポップアップイベントなどを行う複合文化施設として位置づけられていた。 アトリエ・エクリチュール提供#聖水洞(ソンスドン)
-

Features 2024 SUMMER
ソーシャルベンチャーのインキュベーター 聖水洞(ソンスドン)は2010年代半ばからソーシャルベンチャーを支援する機関や団体が集まり、民間主導のソーシャルベンチャーバレーが形成された。今や名実ともに韓国のソーシャルベンチャーの中心地となっており、かつての準工業地域のイメージから脱して斬新で活気あふれる街へと生まれ変わっている。 ルートインパクト提供#聖水洞(ソンスドン)
-

Features 2024 SUMMER
ポップアップストアの聖地 コロナ禍で実店舗が苦戦を強いられていた頃、聖水洞(ソンスドン)は大きく飛躍した。ポップアップストアのおかげだ。ここでは一年を通して多彩なポップアップストアが開設されている。ファッション、アート、音楽、ライフスタイルなどコンテンツもバラエティーに富んでいる。ポップアップストアは今や聖水洞のアイデンティティーを決定づける重要な要素になっている。 バーバリーが2023年に聖水洞で開催したポップアップストア・聖水ローズ。バーバリーのクリエーティブディレクターを務めるダニエル・リー氏の初コレクションで構成され、ストアの内外を華やかに彩るバラのデザインも話題になった。 © バーバリーコリア##聖水洞(ソンスドン)
-

Features 2024 SUMMER
ハンドメイドシューズ、息の長いローカルコンテンツ 聖水洞(ソンスドン)は韓国最大のハンドメイドシューズ産業の集積地として1980~90年代に活況を呈したが、産業構造の急激な変化によって衰退の危機にある。そのため、自治体は様々な支援策で同産業の復興を図っており、家業を継いだデザイナーや職人は若い感性で新たな活力をもたらしている。 地下鉄2号線・聖水駅の駅舎。同地が全国的なハンドメイドシューズの中心地であることを象徴する数々のオブジェが設置されている。 © チェ・テウォン(崔兌源)#聖水洞(ソンスドン)
-

Features 2024 SUMMER
過去と現在をつなぐ赤レンガ 聖水洞(ソンスドン)は、都市再生の代表例といえる。その根幹をなすのが、建築材料として使われる赤レンガだ。ここは軽工業の中心地だったので、1970~90年代に造られた赤レンガの工場や住宅が数多く残っている。地域的・歴史的な特性が息づく赤レンガの建物を保存して価値を高め、特色ある都市景観を生み出している。 カフェ・オニオン聖水。アーティストグループ・ファブリカ(Fabrikr)は、対象に内在する文脈と物性を把握し、それらを自らの造形言語で表現している。同カフェのデザインにも通底しており、建物に残された時間の痕跡を生かすことで街並みに違和感なく溶け込んでいる。 © ホ・ドンウク(許東旭)#聖水洞(ソンスドン) #Features
 KOREA FOUNDATION
KOREA FOUNDATION